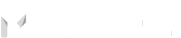- HOME
- 趣味
- プラモデルの作り方講座|初心者が揃えておきたい道具は?塗装のコツも解説
プラモデルの作り方講座|初心者が揃えておきたい道具は?塗装のコツも解説

子どもの頃にガンプラや車・戦車などのプラモデルを作った経験のある方は多いのではないでしょうか。
大人になってからプラモデルを作ると、プラモデルの奥深さにあっという間にハマり、一生楽しめる趣味になります。同じモデルを組み立てるだけでも、組み立て方や塗装などのテクニックによって完成度は段違いです。
しかし、趣味でプラモデルを作りたいけど、初心者だからきれいに作れるかどうか不安で始めることに躊躇しているという方もいるでしょう。
この記事では、プラモデルの基本の作り方から初心者が揃えておきたい道具、塗装のコツまで解説します。
プラモデルの作り方

プラモデルには説明書が付属しており、ただ組み立てるだけなら子どもでも作ることができます。
しかし、プラモデル作りの基本を押さえて丁寧に作ることで、本物のような質感の、完成度の高いプラモデルを作り上げることができます。せっかくプラモデルを作るなら完成度にもこだわって作りたいですよね。
プラモデルにはガンプラや車、戦車・城など、さまざまな種類がありますが、基本的な作り方は共通です。
ここでは、初心者が知っておくべき、プラモデルの基本の作り方を解説します。
内容物のチェック
組み立てたいプラモデルを購入し、まずは開封します。さぁ早速組み立てよう!・・・
とちょっとストップ!
稀に不良品があるので、説明書と照らし合わせて、パーツを確認しましょう。
作る順番を確認
基本は説明書通りの順番でいいと思いますが、
「この部分作るの飽きそうだな」
と思う部分で、先に作れそうなものがあれば作ってしまうのがおすすめです。
完成直前になると、早く完成させたくなってしまってそこまで重要じゃない細部の部分を省いてしまうことがたまにあるので、そういった部分は先に終わらせられると理想です。
完成形をイメージしてニヤニヤ
説明書や、パーツが梱包されていた箱の写真を見て、完成形をイメージしましょう。モチベーションが湧いてきて、思わずニヤニヤしてしまうと思います。
ランナーからパーツを切り離す
プラモデルは、部品が成型された「ランナー」から必要なパーツを切り離して組み立てます。
ランナーとパーツの接合部分は細くなっていますので、指でねじるだけでも取り外すことができますが、完成度を求めるなら専用の「ニッパー」を使ってパーツを切り離しましょう。
パーツを切り取る際には、パーツのギリギリの部分で切り取るよりも1ミリ程度「ゲート」を残して切り離すのがコツです。
慣れない際には、ゲートを残さないことを意識するあまり、パーツギリギリにニッパーを入れ過ぎて、パーツまで切ってしまうリスクがあります。また、パーツに近い位置にニッパーを入れた場合、パーツに負荷がかかってしまい変色・変形してしまう可能性もあります。
遠回りのようですが、ゲートを少し残して切り取ってからゲートを取り除く「ゲート処理」をしてあげることで、ベストの状態でパーツを切り離すことができます。
上級者では、最初に全てのパーツをランナーから切り離す「全切り」と呼ばれる手法で作る人もいますが、初心者のうちはどのパーツか分からなくなってしまう可能性がありますので、説明書の手順通りに必要な部品だけを切り離すようにしましょう。
パーツを組み立てる
パーツは「通常キット」と「スナップフィットキット」で組み立て方が異なります。
・通常キット:パーツ同士を接着剤で接着して組み立てる
・スナップフィットキット:接着剤を使わずにブロックのように組み立てる
スナップフィットキットは比較的新しいプラモデルに採用されており、ブロックのように組み立てるだけで作れますので、初心者でも比較的簡単に作ることができます。
ただし、多くのプラモデルは接着剤を使用する通常キットですので、接着剤を使ったパーツの組み立て方は覚えておきましょう。
プラモデルのパーツの組み立てには、プラモデル用の接着剤を使用します。プラモデル用の接着剤は、プラスチックを溶かす溶剤と接着面を埋める樹脂で構成されています。
接着したい面以外に接着剤が付着してしまうと、パーツが溶けて変色してしまいますので、余計な部分に接着剤が付かないように気を付ける必要があります。
また、プラモデル用の接着剤は、パーツのプラスチックを溶かして接着する仕組みですので、接着剤を塗ってすぐにパーツを貼り合わせても、充分な接着力がありません。
接着面に薄く接着剤を塗って、30秒〜1分程度置いてから貼り合わせることで、しっかりとパーツを組み立てることができます。
部品を組み立てたら、接着面をやすりなどで仕上げてあげることで、接着面を消して、よりプラモデルの完成度を上げることができます。
シールや塗料で仕上げ
パーツを組み立てたら、シールや塗料でプラモデルを仕上げていきます。
プラモデルのシールには、台紙から剥がして貼り付けるだけの一般的なシールと、水に浸けて接着する「デカール」があります。デカールの方が部品とシール部分の質感の違いが目立たず、完成度が高くなるため、プラモデルではデカールが使用されることが多いです。
デカールは、1枚のシートに、各部品に必要な部分が印刷されていますので、必要なデカールだけを切り抜いて使用する必要があります。
水に浸けて台紙から外して転写する形ですが、折れたりズレたりしやすいため、指ではなくピンセットなどを使用するようにしましょう。
また、塗料での仕上げには、大きく分けて3つの方法があります。
・筆塗り
・缶スプレー塗装
・エアブラシ塗装
最も手軽なのは筆塗りですが、筆塗りの場合は筆ムラに注意が必要です。筆ムラを防ぐためには、できるだけ塗料を薄塗りしてあげるのがコツです。
また、一方向だけに塗るのではなく、90度で筆跡が交わるように塗ってあげると、筆ムラが目立ちにくいです。1度で塗るのではなく何度も重ね塗りしてあげることで、金属の質感も出ますし、筆ムラも目立たなくきれいな仕上がりになります。
より、完成度を高くするには、缶スプレーやエアブラシでの塗装もおすすめですが、換気には充分注意しましょう。
プラモデルを作るのに必要な道具

プラモデルを作るためには、最低限ニッパー・やすり・接着剤が必要ですが、その他にも揃えておいた方が便利な道具があります。
プラモデル用の道具は種類も豊富で、用途に応じて揃える必要がありますので、道具を揃えるのもコレクション感覚で楽しむことができますね。
しかし、一気に道具を揃えると費用もかさんでしまいますので、必要に応じて買い揃えていくようにしましょう。
ここでは、プラモデルを作るために、初心者が揃えておくべき道具を紹介します。
ニッパー
プラモデルの部品をランナーから切り取る際にニッパーを使用します。
通常のハサミでも部品を切り取ることはできますが、硬いプラスチックを切ることもあるプラモデル作りでは、ニッパーを使用するのがおすすめです。
プラモデルには、通常のニッパーよりも薄刃のニッパーが使いやすいですね。模型メーカーの販売するニッパーは、通常のニッパーよりも刃先が細かく、ランナーからパーツを切り離すのに適しています。
ナイフ
ランナーから切り取った部品のゲート処理(切り口の修正)や、デカールやマスキングテープのカットにナイフ・カッターを利用します。
デカールを切る際には、ペンのような形状で繊細な作業が可能なデザインナイフを用意しておくと便利です。デザインナイフは、刃先が消耗すると切れ味が悪くなってしまいますので、替刃も合わせて用意しておきましょう。
ナイフを利用する際には、机を傷つけないようにカッティングマットを利用するようにしましょう。
やすり
切り取った部品の切り口を整える、接着部分の合わせ目を消すなど、プラモデルの完成度を高めるキモともなる道具が「やすり」です。
基本の金属製のやすりだけではなく、用途や削りたい部分に合わせてさまざまなやすりがあります。
| プラスチック・金属を削る | 金属製やすり |
| 仕上げの細かい磨き | フィニッシングペーパー |
| 曲面の磨き | 研磨スポンジシート |
金属製のやすりには「平」「半丸」「丸」などの形状があり、部品の形状に合わせて使い分けます。
やすりには100番や2,000番・3,000番といった「番手」があり、数字が小さいほど目が粗く大きく削れるのに対し、数字が大きくなるほど目が細かく磨き作業に適しています。
大きい番手のやすりの場合、目詰まりを防ぐために水を付けて使用する「耐水ペーパー」を利用します。
組み立てや部品のディテールアップのために、ピンバイスやドリルを用意しておくと便利です。
ピンセット
プラモデルの小さな部品やデカールを掴む際には、ピンセットを使用します。
ピンセットにはさまざまな形状があります。
・ストレート
・つる首
・逆作動
サイズもさまざまなものが販売されていますので、自分の手になじむピンセットを見つけるようにしましょう。
接着剤
プラモデルの部品の組み立てには、接着剤が必要です。
フタに接着剤を塗るためのハケが付いた、プラモデル用の接着剤の他、組み立てる部品に合わせて接着剤も使い分けましょう。
| プラスチック・金属の接着 | 瞬間接着剤 |
| 透明部品・メッキ部品の接着 | クリヤー |
| 発泡スチロール・紙・木の接着 | クラフトボンド |
その他、安全性が高い柑橘類から作られた「リモネンセメント」などもありますので、小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心です。
部品の組み立てだけではなく、誤ってパーツを破損させてしまった際など、瞬間接着剤で補修することができます。
塗料
プラモデルを塗装することで、金属やゴムなどの質感を表現して、完成度を大きく高めることができます。
塗料の種類は、大きく分けて「缶スプレー」と「ビン入り」の2つのタイプがあります。
・缶スプレー:一気に広い面積を塗るのに適している
・ビン入り:筆塗りやエアブラシ塗装に利用できる
初心者は、筆塗りから始めるのが手軽です。ビン入りの塗料を使う際には、薄め液などで希釈して塗装します。
また、ビン入り塗料には、目指す仕上がりや塗り方に合わせて3つの種類があります。
| 塗膜が強く乾燥が早い | ラッカー塗料 |
| 水溶性で取り扱いが簡単 | アクリル塗料 |
| 細部の筆塗りに使用する | エナメル塗料 |
筆塗りの場合、塗り筋が出やすく仕上がりに影響しますので、塗り筋を少なく塗れるようになるまで練習しましょう。
塗装の精度を向上させるためには、下地となる「サーフェイサー」を使用するのがおすすめです。
また、エアブラシやコンプレッサーを用意して、エアブラシ塗装をすれば、プラモデルの完成度を格段に高めることができます。
プラモデルをきれいに作るコツ

プラモデルは下処理・組み立て・仕上げのそれぞれの工程を丁寧に行うことで、仕上がりの完成度を高めることができます。
なかなか思ったような仕上がりでプラモデルを作れないという方は、各工程で正しい作業ができていない可能性があります。
ここでは、初心者がワンランク上の仕上がりでプラモデルを作るためのコツを解説します。
ゲート処理を行う
プラモデルの完成度には「ゲート処理」が丁寧に行われているかどうかが大きく影響します。
ゲート処理とは、ランナーから切り離したパーツに残った余計な部分「ゲート跡」を取り除く処理のことを指します。
ゲート跡が残っていると、組み立てた時に不自然な仕上がりになりますし、接着面にゲート跡が残っていた場合、組み付けた部品に隙間が出ることもあります。また、塗装の際にゲート跡が残っていると、塗膜に凹凸ができてしまい美しい仕上がりになりません。
しかし、ゲート跡を残さないように意識し過ぎると、パーツまで切ってしまったり、パーツに負荷をかけたりして、変色や変形の原因になってしまいます。
ですのでパーツをランナーから切り離す際には、ゲート跡を1mm程度残して、ゲート処理で仕上げてあげるようにしましょう。
ゲート処理には、デザインナイフで切り取る、やすりで削るなどの方法があります。デザインナイフで切り取る際には、慣れるまでパーツに切り込みを入れてしまったり、怪我をしてしまったりする可能性がありますので、初心者のうちはやすりでのゲート処理がおすすめです。
やすりでのゲート処理では、部品にあった形状のやすりで、ゲート跡と部品の境目がなくなるまで削ります。
そのままでは、やすり跡が残ってしまいますので、番手の大きいやすりやコンパウンドで磨いて、やすり跡を消してあげると美しい仕上がりになりますね。
スミ入れ塗料を使う
機械部品のパネルラインなど、プラモデルのディテールの立体感を増すためのテクニックが「スミ入れ」です。
プラモデルでは、1枚のプラスチックに凹凸の形で表現されている部分が、実際の車などでは別の部品の重なりで構成されて影が発生します。スミ入れは、パーツの凹凸にサラッとした塗料を流し込み、陰影を表現します。
スミ入れに使う塗料は粘度が低くサラっとした配合になるように調整します。スミ入れ塗料は、スミの流し込みに適した粘度に調整されていますので、初心者でも簡単にスミ入れをすることができます。
筆タイプのスミ入れ塗料での流し込みが難しいという方は、ペンタイプの「スミ入れ用ペン」を使うのもおすすめです。
スミ入れをしたい部分からスミがはみ出してしまった場合は、プラスチック消しゴムなどで修正できますので、少々のはみ出しは気にし過ぎなくても大丈夫です。
シールの余白をカットする
シールを貼って仕上げたプラモデルの完成度をより高めるなら、シールの不要な余白をカットしてあげましょう。
特にデカールを貼る場合、プリント部分よりも大きく切り過ぎると、余白の部分が目立って仕上がりが美しくありません。
デザインナイフなどを使用して、できるだけプリント部分のギリギリでデカールを切り取ってあげるようにしましょう。
ただし、あまりギリギリを狙い過ぎると、プリント部分まで切り取ってしまったり、デカールにプリントされた印字が水で滲んでしまったりする可能性があります。
余白が少ない方が仕上がりは美しいですが、慣れるまではある程度の余白は許容範囲として考えてあげるようにしましょう。
趣味人倶楽部でプラモデル好きとつながろう

プラモデルは1人でも楽しめる趣味ですが、プラモデル仲間と作品を見せあったり、こだわりを話したりすることで、より楽しみが広がります。
プラモデル好きの仲間を作りたいなら、趣味でつながる大人世代のSNS「趣味人倶楽部(しゅみーとくらぶ)」のコミュニティ機能を活用するのがおすすめです。
趣味人倶楽部のコミュニティには、初心者から「モデラー」と呼ばれるプラモデル上級者まで、さまざまなプラモデル好きが交流しています。
頑張って完成させた作品を見てもらうだけでも、プラモデル作りのモチベーションアップにつながりますし、製作のアドバイスをもらえば、自分の作品の完成度をさらに高めることができますね。

コミュニティではこのような写真が投稿されています。

まとめ:慣れてきたらオリジナリティを出すのもアリ

プラモデルをただ組み立てるだけなら子どもでもできますが、完成度の高いプラモデル作りは、一生の趣味にもなる奥深い楽しみです。
説明書通りに組み立てるのに慣れてきたら、プラ板やランナーなどの素材、パテを使ってオリジナルのカスタムを施すのもおすすめです。上級モデラーの中には、プラスチックなどの完全な素材の状態からモデルを組み上げる、フルスクラッチで楽しんでいる方もいます。
プラモデルは作るだけではなく、作ったプラモデルを飾る楽しみもあります。コレクションケースなどを購入して、自分の力作を飾って楽しむのも良いでしょう。
細かい作業が好きな方は、趣味でプラモデル作りを始めてみてはいかがでしょうか。