すべての投稿
太宰治「惜別」
これも大変面白かった。 戦争末期の昭和19年に日本文学報国会からの委嘱を受けて書かれたものだそうだが、太宰は前からこのテーマで書きたかったようである。 昭和20年、戦後に出版され、副題として「医学徒の頃の魯迅」とあったらしい。 中国人の魯迅が日本の医学を学ぶために...
イサベル・アジェンデ『精霊たちの家』
池澤夏樹編世界文学全集のⅡ-07である。 当初、この作家名は聞いたことがないし、このタイトルも全く知らなかった。ペルーの生まれで、チリで育ち、南米文学では有名な作家らしく、マルケスの『百年の孤独』とも並び称される作品だという売り言葉もあまり反応しなかった。だから、...
ジョゼフ・コンラッド『ロード・ジム』
ボクシングの話かと思った。ROAD GYMかと。しかし違った。原題はLORD JIMである。神のようなジムかな。そう言えば、昔ジョージ・ハリスンの曲に「マイ・スイート・ロード」というのがあったが、何だろう「甘い道」とはと、高校生のわたしは思ったものだった。あれもR...
太宰治『津軽』
昭和19年の作品だとのこと。 戦争中だ。 この中でも国防上詳しくは書けないというような記述が時折ある。あと、配給の酒をどうしたという話しがよく出てくる。 この作品は紀行文と言えばいえる。自分の生まれたところに帰りいろんな場所に行き、友人や親類の人たちと旧交を温めた...
若山牧水『みなかみ紀行』
面白い! 牧水の紀行文関係の文庫本としては、岩波の『新編みなかみ紀行』、中公の『みなかみ紀行』、講談社文芸文庫の『若山牧水随筆集』があるが、全部面白い。 昔は、写真が無かったので、例えばある景色を見て感動すると、牧水の場合は歌を作る。 牧水の歌がどういうふうにし...
二瓶哲也「ヒマラヤ杉の年輪」
文学界8月号にある。 40歳の私が病院清掃の仕事につき、そこで70歳を超えた同僚とのやり取りがあって、そのうち看護補助として働いている22歳の若いきれいな女性がに恋をして云々と物語は続く。病院清掃の現場がリアル。たぶん、二瓶さんはこの仕事の経験があるのだろう。最...
岡崎祥久「キャッシュとディッシュ」
文学界8月号に掲載。 岡崎さんのプロフィール。ウィキペディアより。 岡崎 祥久(おかざき よしひさ、1968年8月17日- )は、日本の小説家。東京都出身。早稲田大学第二文学部卒業 作風。 デビュー以来、「現代のプロレタリア文学」あるいは「ニュープロレタリア文...
加賀乙彦『フランドルの冬』
小学館のP+D BOOKSというペーパーバックのような体裁の、粗末な紙質で文庫本より少し大きめの本を買って読んだ。本なんてほとんど買わないのだが、図書館が完全閉館になってしまったので、何か読もうと思って書店に行って目についたこの本を買ったのだ。 実はこれは、大学を...
加藤典洋『太宰と井伏ーふたつの戦後ー』(講談社文芸文庫)
今年71歳で亡くなった加藤さんの本をポツリポツリと読んでいる。画期的な村上春樹論だった「世界の終わりから」、戦後日本のねじれについて書いた有名な『敗戦後論』、『戦後入門』、そしてここで紹介した『九条入門』などを読んできた。加藤さんは日本人にとっての戦後とは何なのか...
メアリー・マッカーシー『アメリカの鳥』
世界文学全集Ⅱ‐04。 面白かった! 母が音楽家の家で育った、マザコン気味の息子ピーター・リーヴァイが19歳になって、フランスに留学し、そこでいろいろなことを経験する物語。時代は1965年。 ピーターはカントの道徳律を信奉している。 他者を手段と見なすなということ...
ドストエフスキー『虐げられた人々』(新潮文庫)
40年前に読んで、ネリーの可愛らしさが記憶に残っていたし、中央公論社の詩人のシリーズの一つ、室生犀星の巻を読んでいたら、犀星のドストエフスキーへの感想のようなものが欄外にあって、その中でこの『虐げられた人々』が取り上げられていたので、懐かしかった。犀星は「私は寂し...
古川真人「窓」
図書館で新着図書として古川さんの『ラッコの家』の単行本があったので借りてきた。その中には芥川賞候補となった「ラッコの家」(既読)ともう一つ「窓」という中編の作品があったので、それを読んでみた。 古川さんはまだ30代の若手の作家で、一昨年新潮の新人賞をとっている。...



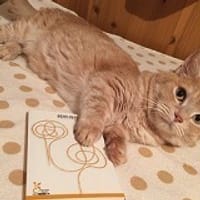






コメント 0