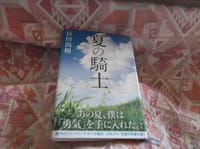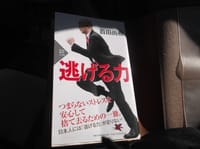「百田尚樹著」の日記一覧
『幻庵下』(百田尚樹著)(最終回)
エピローグ 秀和をもって近代碁が始まった。 旧来の家元制度では囲碁の未来はないと見た村瀬秀甫は、 「方円社」を創設した。 方円社は旧家元をしのぐ勢いを得て、碁打ちたちもこぞって方円社に入った。 方円社の支援者には、井上馨、岩崎弥太郎、大隈重信、渋沢栄一、山県有朋など、錚々たる人物が名を連ねている。 秀甫がいなければ、日本の囲碁は明治維新とともに滅んでいたかもしれない。 「近代非凡人31人」の…
『幻庵下』(百田尚樹著)(続続)
物語はまだ終わらない。因碩の生涯は晩年さらに波乱に富んだものになる。 あの3局は己のすべてを出し切った。秘術の限りを尽くしたが、秀和の先を崩せなかった。それが碁だー。 安田秀策の強さは因碩も耳にしていた。まだ15歳ながら、次の跡目候補と言われているほどだ。 「秀策は初段ということで、向こう二子で四局打ちました。ところが、一番も入りませんでした」 「五段のお前が四局棒に負けたか」 因碩と秀策は3…
『幻庵下』(百田尚樹著)は、囲碁の伝統と文化は守られ、戦後、韓国や中国に広まっていく。囲碁で人間を打ち破るAIを作る、人知を超えたAIの誕生を考えた、と
安藤如意原著の『坐隠談叢』。資料的には唯一無二と言えるものではないが、 名前や年代の誤りは少なくないが、当事者ならではの生々しい記録は他の書の追随を許さない。 大広間に集まった本因坊丈和、安井仙知、井上因碩、林元美を前にして、「本因坊丈和殿の名人碁所願いについての儀である」と。 寺社奉行が本因坊丈和に名人碁所を官許したのだ。 丈和は名人碁所に就いて当然の碁打ちであった。ただ、その就位は健忘術策…
『幻庵中』(百田尚樹著)は、願うのは、寺社奉行が丈和の名人碁所をゆるさぬことだ。因碩はそれを一縷の頼みとした、と
17歳になった服部立徹。 葛野丈和と対局した。 前日の桜井知達に打った碁で何かを掴んだ感触があり。 父の服部因淑は、「もはや先の碁ではない」と言った。立徹は浅草の清光寺の碁会で丈和と打った。 丈和の持つまだ見えない強さが顔を出したものなのか。 立徹が丈和に肉薄している。 元丈は立徹と打ってみようと思った。 つまりは心から服部立徹の才を認めたということだ。 後世の碁打ちたちが「服部立徹こそ、まさし…
『野良犬の値段下』(百田尚樹著)は、ホームレス支援団体に、匿名の高額寄付があったという、いい話が聞けてよかったと言う
「やるんだ!」 松下は高井田を睨みつけ、鋭い口調で言った。 「何も高井田さんに、俺を殺せとは言っていない。 だから、薬で安楽死させてくれ」 高井田は 河川敷に、影山貞夫、石垣勝男、大友孝光、それに松下和夫を集めた。 これから行う「誘拐事件」の計画と作戦の概要をあらためて語った。 ネットを使ってサイト上で展開するアイデアを出したのは石垣だった。 このアイデアによって「劇場型」の骨格が固まった。…
『野良犬の値段上』(百田尚樹著)は、ネット社会の誘拐サイトの犯罪を描く
佐野光一は、 スマートフォンの電源を入れた。 「犯人は意味のないことをやる人物と考えることができる。これは犯人の欠点かもしれない」 ネットを使った劇場型犯罪、ホームレスの誘拐、そして人質とは無関係な新聞社やテレビ局に対する身代金要求ーまさに異例ずくめの殺害だった。 しかし鈴村は今回の松下の殺害が単なる偶然とはどうしても思えなかった。(下巻につづく) 2024年2月12日読了。 *この…