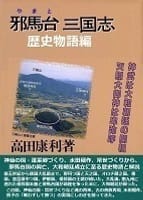「古代史」の日記一覧
日本書紀を訪ねて「歴史編〈三〉大化の改新」大阪・難波宮跡
歴史学講座「創世」葛飾塾;神武東征に登場する「ヤタガラス」とは?
日本書紀を訪ねて「歴史編〈二〉仏教公伝」向原寺周辺 奈良県明日香村
「ほっと氏の野鳥の話題」への御礼と、次の予告
ふしぎな、日本の民俗 「ほっと氏の野鳥の話題」№5~№60の計56回にお付き合いいただきどうもありがとうございました。 掲載を続けている間は閲覧してくださった方々をはじめ、いただいた拍手やコメントにはたいへん励まされました。ここに改めて御礼申し上げます。 野鳥の話はまだかなりあるのですが、ひとまずこのくらいにして、私、びたせんの現在いちばんの関心事であります、日本の民俗、の話題に勝手に移…
日本書紀を訪ねて「伝説編<四>衣通郎姫」
歴史学講座「創世」アスカ(明日香: 奈良県)の原初的由来
日本書紀を訪ねて「伝説編<二>神功皇后」玉島川(佐賀県唐津市)
日本史 アップデート「大化改新」蘇我氏 滅びず影響力
日本書紀を訪ねて 「神武東征伝説編〈一〉 (奈良・宇陀、桜井)
〔六根清浄と智慧の源流〕羽衣伝説
ここで、ちょっと一息。羽衣伝説は世界各地にあるらしい。日本では、『近江国風土記』記載の余呉湖にまつわる伝説、『丹後国風土記』にある京丹後市峰山町を舞台とする伝説が有名だ。 『丹後国風土記』では、悲劇に遭った豊宇加能売(とようかのめ)が男神天照大神、天照大御神、火瓊瓊杵、丹後海部家に寄り添ってきた豊受姫とどう関係するのか定かでないが、この機会に「羽衣伝説」を通して、当時の天女の心意気と共に、俗人…
〔六根清浄と智慧の源流〕牛頭天王と熊野権現と山王権現
①牛頭天王が磐座に降り立ったとする伝承は、各地に存在する。豊受大神と天照大神を祀る籠神社奥宮の磐座二座も、熊野権現が天降る神倉神社のゴトビキ岩・水徳の神が降り立つ比叡山系牛尾山山頂の金大巌(こがねのおおいわ)も、牛頭天王が姿を変えて降臨した磐座と見てよかろう。 〔籠神社奥宮の眞名井(まない)神社〕(宮津市)、社殿背後の左右に磐座二座が鎮座して、右側の磐座主座(本宮)祭神は豊受大神、左の磐座西座…
日本書紀を訪ねて 「神代編〈五〉 天孫降臨」霧島山(宮崎・鹿児島)
〔六根清浄と智慧の源流〕南伝仏教の東アジア流入
①我が国では縄文時代の昔から、五帝期の神仙思想、天竺風の習慣・来世観・石の文化、さらに初期仏教に似た教義が根づいていた。このことから、「東の海上に神仙郷がある」との噂が何度も春秋期の中国に伝わり、斉の威王・宣王、燕の昭王らが東海上に探検隊を送るのであり、儒教を弾圧した秦始皇帝も神仙思想に心を開き、不死不老の仙薬を手にしたいと徐福を遣わしたのだ。 邪馬台国時代、この種の神仙観が鏡の模様となって現れ…
〔六根清浄と智慧の源流〕謡曲白髭と仏法・山王信仰の聖地
①湖西線高島駅から南に降ると、比良・志賀・蓬莱・和邇、比叡山坂本・大津京など古代にちなむ駅名が連なっている。比良は海神族と思しき比良明神、志賀は志賀海神社や安曇氏、蓬莱は海神・大山祇神との因縁が深い。和邇は海神配下の鰐族末裔だ。志賀の真西には、蓬莱山がそびえており、比叡山坂本は日吉大社の鎮座地、大津京は天智天皇が近江大津宮を開いた処である。 振り返ると、富士山・熊野山・熱田神宮の地がかつて蓬莱山…
〔六根清浄と智慧の源流〕シュメル神話と十六菊花紋
〔六根清浄と智慧の源流〕宗教はミトラ教に始まる
〔ミトラ教〕、牛の角を生やした太陽神の女神ミトラは、シュメル神話に出てくるメソポタミア生まれで雄牛の角をもつ王冠をかぶった太陽神アン(天の神)の流れを汲むらしい。 ☆前三○○○年代、太陽神アンは救世主、契約を司る神として、メソポタミアやオリエントで崇められ、後にヘブライ社会、ギリシャ・インド・キリスト圏に姿形を変えて広まった。 ☆皇室の紋章である十六八重菊花紋は、シュメルの太陽神アンの象徴、ある…
〔六根清浄と智慧の源流〕太陽神の女神ミトラと牛頭天王と仏陀ゴータマ
①西アジアでは、イラン高原でゾロアスター教の興る以前から、ミトラ多神教など様々な神々がイラン系アーリアの間で信仰されていた。世界最古のミトラ教は、ゾロアスター教、ギリシャ教、仏教、キリスト教、中央アジアで救済を説いた弥勒信仰などに多大な影響を及ぼしてきた。 その一つ、頭に角を生やした太陽(光明)神の女神ミトラ(ミスラ)を祀る密儀宗教は、人気が高く、アケメネス朝ペルシャ帝国(前五五〇~前三三〇年)…
〔『邪馬台三国志』歴史物語編、解説編〕今秋に同時発売のお知らせ
ため込んだ古代史への周回 8
コロナウイルス騒ぎでついに全国的に緊急事態宣言がでました。 あとはこの国民の民度が問われるだけです。 政治はそれなりのレベルで稼働していますので後は国民の 知的レベルが試されるだけです。 パチンコ屋はまだ営業自粛してないそうですが、ここへ行く 事が死活問題ではないので、行かなければいいだけです。 それやこれやでこの古代史もなかなか筆が進みません。 あまりにも書きたいことが多くて行きつ戻りつ…